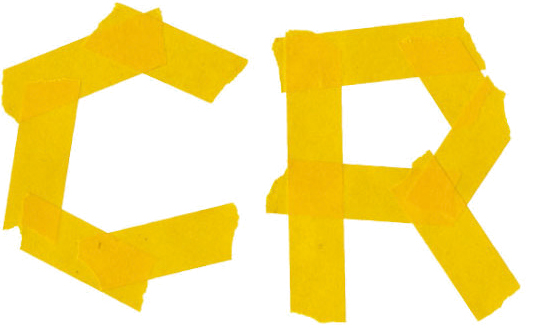いわきでのお披露目上映の日にちと会場が決まりました。
来年2月16日(日)、いわき芸術文化交流館アリオスにて行います。
上映後には懇親会を予定しています。FUKUSHIMA VOICEのスタッフが直接映画制作について話をするなど鑑賞いただいた皆さまとの交流の場を設けたいと思っています。
上映スケジュールの詳細は決まり次第お知らせします。
お世話になった方々を始め、多くの方にお越しいただきたいと思います。
(橋本)

Category Archives: お知らせ
東京デザイナーズウィーク2013 学校展 準グランプリ受賞!
予告 創造的復興:カタストロフィーと芸術−11月9日(土)
「Wall Art Festival」
「Wall Art Festival」展示開催
筑波大学大学院2年生の田中みさよさんが中心となって、
「Wall Art Festival」の展示が始まりました。
「インド×アート×学校 Wall Art Festival」
日時:10月7日(月)〜10月15日(火)
時間:9:00~18:00
会場:6Aエントランスギャラリー
<トークイベント>
「交流の中で生まれるアートと、その可能性」
日時:10月15日(火)18:30~20:30
会場:筑波大学6A208
内容:Wall Art Projectのオーガナイザーや参加アーティストの方たちをゲストに迎え
トークイベントを開催します。イベント終了後、場所を移して懇親会も開催します。
Wall Art Festivalは、「アート×学校×支援!~アートがつなぐ笑顔。アートの力で生まれる絆。
~」をスローガンに掲げる芸術祭です。インドの中でも教育システムやインフラの整備が未だ
途上の村で、学校を舞台として過去4回開催されてきました。2010年2月に第1回が開かれそこ
から年に1度の芸術祭として回を重ね、第1~3回はインド・ビハール州・スジャータ村にて、
第4回はインド・マハラーシュトラ州・ダーネー地区ガンジャード村にて行われ、来年2014年も
ガンジャード村での開催が決定しています。
「この芸術祭のストーリーは日本の学生50人が、インドの小さな村の学校に校舎をプレゼント
したことから始まった。いちばん大切なのは、学校を建てることではなくて、建てた後の支援
だということに気づくのはしばらくたってから。”なんとかしなければ!”と始まったのが、
校舎の壁をキャンバスにした、白い壁さえあれば実現することを伝える芸術祭だった。
「アート×学校×支援」を掲げ、お金に換算できないアートをこの世界の各地に広めていく、
それが私たちの野望。
(「Wall Art Festival Book インドしろいかべのキセキ」より)
このプロジェクト自体は、震災を契機に生まれたものではなく、そして震災復興を目的として
進んでいる訳でもありません。しかし、人と人とがアートを介した関わりによってつながって
いく試みを実践しているという点において、創造的復興プロジェクトとWall Art Festivalは目的
の通うところがあるのではないでしょうか。
震災の起きた2011年、その年の5月28、29日に福島県郡山市の「ビッグパレットふくしま」
にて「Wall Art Festival in FUKUSHIMA」が開催されました。インドからのメッセージを避難さ
れている方々へ届けること、またWAF2011にアーティストとして参加された方々による展示・
ライブやワークショップなどが催されました。
このイベントの成功は、インドで実践されてきた”アートを通じた関わり”のつながりの上にあ
ります。交流の中で生まれたつながりを自然と、次のつながりへつないでいくこと。この真摯
な姿勢と、そして関わる人々の情熱によってまわっているサイクルが、芸術祭を力強く前へ押
し進めています。Wall Art Festivalの活動をこのギャラリーで紹介させていただくことで、触れ
られた方ひとりひとりに、何か気づきがあれば幸いです。どうぞごゆっくりご鑑賞ください。
人間総合科学研究科専攻総合造形領域博士前期過程2年
Wall Art Festival 報告会実行委員会
田中みさよ

FUKUSHIMA VOICE撮影合宿
ドキュメンタリー映画制作プロジェクト『FUKUSHIMA VOICE』は9月1日から8日まで撮影合宿を行いました。
初日には『未来会議inいわき×FUKUSHIMA VOICE』を開催し、未来会議の様子を撮影しました。この未来会議が本映画の軸になります。
[未来会議inいわき×FUKUSHIMA VOICE]
https://www.facebook.com/events/1396182743935344/

2日目からは朝早くから取材に出かけ、夕飯の後はラッシュとミーティングを繰り返す毎日でした。
漁師さんや初代フラガール、農家、弁護士、ラジオ局、仮設住宅、学校の先生、サーファー、アーティストなどなど、、さまざまな立場の方を取材しました。




学生たちはそれぞれの撮影現場でその場ならではの雰囲気を肌で感じ、カメラワークや取材テクニック、対象者との関係作りなどたくさんのことを学び、日を追うごとにいい映像を撮りたいという気持ちが強くなっていました。
私たちは取材を通じて震災関連のことだけでなく対象者の人生にも触れ、映像に残すことの責任の重さを感じると共に映画作りの奥深さを知りました。
今回の撮影合宿では様々な方にご協力いただきました。取材を受けてくださったいわきの皆さま、ご支援くださった皆さま、本当にありがとうございました。今後は皆さんの声を一つにしていく作業に入ります。完成・上映は11月末を予定しています。福島の声を世界に発信していくためにこれからの活動もメンバー一丸となって取り組んでいきます。
(橋本)
THEパーティー「ダ・ヴィンチ体操」Youtube
7月27日(土)28日(日)におこなわれた、
週末アートスクール・イン・つくば〜感じて・見て・なりきり
レオナルド・ダ・ヴィンチ!?〜
で大好評でした、THEパーティーさんの「ダ・ヴィンチ体操」が
編集されYoutubeにアップされました。
楽しい「ダ・ヴィンチ体操」ぜひご覧ください!
(赤木)
FUKUSHIMA VOICE進行中!
FUKUSHIMA VOICEのドキュメンタリー映画制作概要が決まり、学生は4チームに分かれ本格的な活動が始まりました。
9/1(日)にいわき市で映画撮影用の「未来会議inいわき×FUKUSHIMA VOICE」を開催し、未来会議で生まれてくる人々の声のうねりの全体像を捉え、またそこに参加した個人をも見つめていくことで一人一人の「声」と個の集合体である「大きな声」を描き出すことを試みます。
未来会議への参加はいわき市内外問いません、ぜひ皆様の声を聞かせてください。(橋本)

「未来会議inいわき×FUKUSHIMA VOICE」
http://www.facebook.com/events/1396182743935344?notif_t=plan_admin_added/
「未来会議inいわき」はこちら
http://www.facebook.com/miraikaigi/
創造的復興:視点構築論2・第10回目の予告と関連展示のお知らせ
視点構築論2・第10回目(最終回)は、美術家の開発好明さんにお越し頂きます。開発さんは、2011年の東日本大震災と原発事故以降、トラックにアート作品を積み込み、日本列島を縦断しながら各地でチャリティー展を開催した「デイリリーアートサーカス」や、福島県 南相馬市に政治家限定の無料の休憩施設をオープンし、毎月15日にイベントをおこなう「政治家の家」、青森 から福島にかけての湾岸地域の人々をインタビューした「言葉図書館」、 南相馬市鹿島区北屋形の獅子神楽を記録したDVD「北屋形の神楽 終わりの始まり」の監督など、幅広いプロジェクトを精力的に実施 しています。
『視点構築論2・第10回目 ゲスト:開発好明』
会場:筑波大学 6A棟208教室
日時:6月28日(金)16:45〜18:00
視点構築論2での開発好明さんの講義に合わせて、福島県南相馬市鹿島区に伝わる伝統芸能、北屋形の神楽を復活させようと制作された『北屋形の神楽 終わりの始まり』を上映します。
『北屋形の神楽 終わりの始まり』
会場: 筑波大学 6A棟エントランスギャラリー
日時: 6/25(火) -6/28(金) 10:00〜17:00

講義、展覧会ともにどなたでも参加できます。(片岡)
三陸視察ツアー
6/1,2に、今年も一泊二日の三陸視察ツアーを行いました。震災から二年が経ち、被災地は今どのような状況であるか自分たちの目で確かめます。今年は学生、教員合わせて約40名が参加しました。
一日目はまず石巻の復興商店街を訪れ、各自商店街のお店や高校生が中心となって運営している食堂などで昼食を取りました。
その後石巻沿岸部、門脇地区へ向かい門脇小学校を見学、がんばろう石巻・ありがとうハウスを訪問し、ありがとうハウスの尾形さんの被災体験をお聞きしました。実際の状況と報道との違いがあったこと、「来年、再来年のことより明日を見たい」という話はとても心に残りました。
被災地は昨年よりもがれきの山は減り、津波で流された跡は草地や空き地が広がり人の気配のなさに物悲しさを覚えました。


宿泊先の牡鹿半島に入り、現地でボランティア活動されている方から震災直後の混乱状況や、人口減少など現状の問題や取り組みなどをお聞きしました。

宿泊先では夕飯後、一人ずつ一日目の感想を話しました。「実際に来てみたけど実感が沸かなかった。想像することの難しさを感じた」「無力感を覚えた」「メディアを通してでなく自分の目で確かめられた」などの感想があり、困惑した様子も見られましたがみんなで意見を共有でき有意義な時間を持つことができました。
二日目はまず女川町を訪れ、津波が押し倒した鉄骨の建物の見学、続いて向かった南三陸地区の復興商店街では南三陸のならではのご馳走を頂き、また安藤先生の復興住宅を見学しました。

最後に東松島のおのくん制作現場を訪れ、仮設住宅の方たちが生き生きと制作にあたっている姿を見ることができ、無力感を覚えた一日目から復興支援はできることから始めればいいと希望を持つことができました。

今回の三陸視察でも多くの方々にご協力いただき、また貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。
参加した学生は自分の目で見て感じたことをチームのみんなに報告し、今後の活動に生かしてほしいと思います。(橋本)